おまち歩きと静岡弁の話だもんで
静岡人は自分たちが標準語を話していると思っている。
県外に出て、その地域の人にきょとんとされてから初めて自分の標準語が少し変かもしれないと気付く。
でも、まだ「少し変な標準語」くらいにしか感じていないので、「それ、方言だよ。」と指摘してもらったほうが本人の為だと思う。
私の考える静岡弁の特徴
①単語のアクセントが変 (アクセントが標準語とは違う。主に最初の音にアクセントが付く場合が多い。)
例:市役所(しやくしょ) 俺(おれ) 嫌(いや) 午前(ごぜん) など
②「ばか~」を多用 (副詞としての「ばか」 「とても」「すごい」と同義)
例:「これ、ばかしょんない。」 訳「これはどうしようもないですね。」
③標準語に同じものはあるけれど使い方が独特で他の地方の人には伝わらない、または違和感がある
例:おまち=市の中心街 センター=新静岡センター
(私見です)
おまちに行くだよ!
静岡市の中心部を静岡市民は「おまち」といい、子供の頃はおまちに行くというのがそこそこなイベントだった。
大学で初めて県外に出てその地域の中心地に遊びに行ったとき、そこを「おまち」と言ってみんなに笑われた。
当時の私は、そこを「おまち」と呼ばないならなんというんだ?と疑問に思ったが、
単純にその地域名を言えばいいと言われた。
なるほど、東京などは「おまち」がいっぱいあるから「銀座」「新宿」「渋谷」等いわないとわからないもんなぁ。
私が当時住んでいたのは静岡とそう変わらない規模の街だったんだけどな。
まぁそんな昔話は置いといて、おまちへゴー!
静岡市で「センター」と言えば新静岡センターだった(過去形)
静岡鉄道の駅とバスターミナルがある静岡の交通拠点がこの新静岡センター、ではなく新静岡セノバ。
新静岡センターとは2009年に閉店するまで、おまちの玄関口として市民に親しまれていた旧ターミナルビルのこと。
他のデパートに比べ、駅ビル型なのでカジュアルで行きやすい。
多くの人がこのビルを「センター」と呼んだ。
「センターで待ち合わせしよう」「センターに買い物に行こう」と言うだけで、
それを聞いた静岡市民は「はいはい、センターね。」となるのだ。
今はもうないけれど、私の心の中ではいつまでも静岡のランドマークだし、センターといったら新静岡センターだ。
(あくまでも私見です)


駿府城公園は静岡のセントラルパークだ!(私見です)
今年(2023年)の大河ドラマ『どうする家康』の主人公・徳川家康の築いた駿府城。
その跡地に作られたのが駿府城公園だ。
正式名称は駿府城公園だが、静岡市民の多くは以前からの名前である駿府公園と呼ぶ。
今でこそ「東御門(ひがしごもん)」「巽櫓(たつみやぐら)」「坤櫓(ひつじさるやぐら)」等の駿府城の建物も復元されているが、
昭和の頃は城らしいものといえばお堀くらいで、公園内もどちらかといえば欧米の公園を真似したような作りだった。
城っぽさを感じられなかったため、城の部分がなかったのかどうかはわからない。

ここは新静岡センターとともに子供の頃からよく遊びに出かけた場所。
子供の頃は、園内にある児童会館といういかにも昭和な科学館で遊ぶのが好きだった。
児童会館の中に入るとロボットが出迎えてくれた。
あれ、名前とかあった気がするけどなんだっけ?
調べてみたら名前は『カンちゃん』。
なんと手塚治虫がデザインしたとのこと!
懐かしいなぁ、あれ。
今は静岡駅南口にある『静岡科学館 る・く・る』にいるらしい。
あれ…じゃなくてカンちゃん。
他にもいろいろあったが、一番好きだったのは交通ジオラマだ。
リアリティのあるジオラマとその中を走る鉄道模型をずっと見ていたくて、
電車が止まるとボタンを押してまた走らせるということを繰り返していた。
児童会館はずいぶん前に取り壊され、現在は静岡科学館 る・く・るにその役目が引き継がれている。
子供の頃は行くのが楽しみで仕方がなかった駿府公園だが、
高校生になると放課後寄り道しておまちに行くときに、自転車で通り抜けるくらいになった。
でも、春夏秋冬で違う風情になる公園を見るのは好きだった。
まぁ、チャリで通り抜けるだけなんだけど。
今回行ったときは、次の日から開催される『大道芸ワールドカップ』の準備中だった。
大道芸ワールドカップも面白いのだが、私は仕事が土日だったので数回しか見ていない。
静岡市民としてちょっと恥ずかしい。
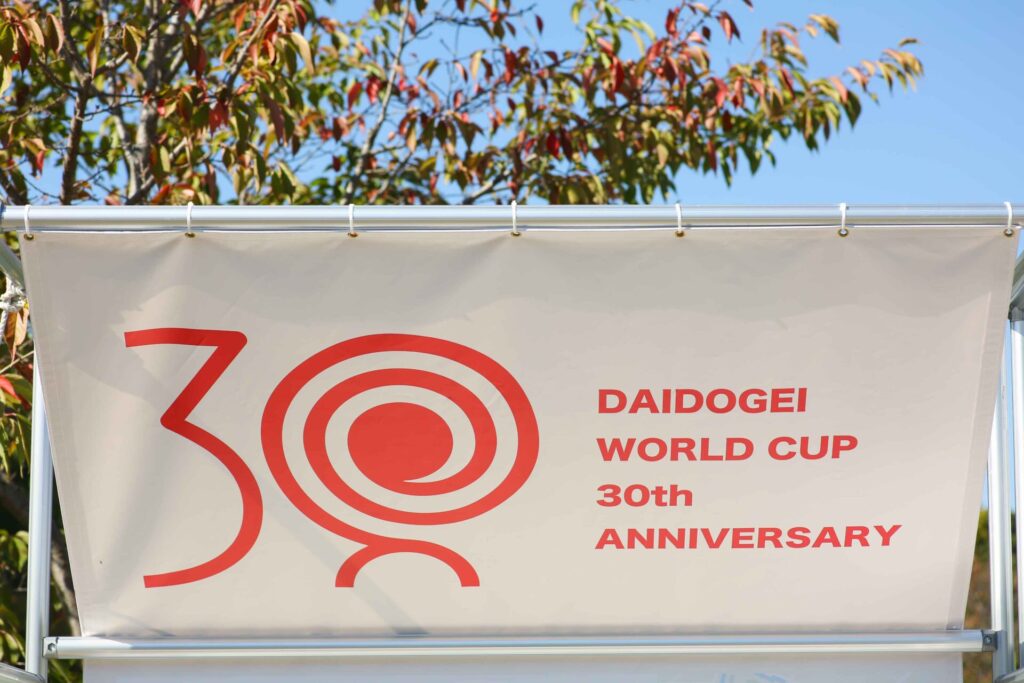
ごせっぽいとは?
静岡弁の中に「ごせっぽい」がある。
意味は、・清々する・スッキリしているさま などで、語源は「御所っぽい」だそうだ。
私が昔聞いた話では、徳川家康公が晩年駿府城で大御所として権力をふるっていたことから、
大御所(家康公)のようにチマチマしていなくて悠々としたさまをいうとのことだったが、それでは「清々する」という意味とは違ってくる。
調べてみたら、家康公が温暖で清々しい駿府(駿府城?)を御所っぽいと言ったという説があるようだ。
幼少期・中年期・晩年期に駿府にいた家康公が唐突に「ここは御所っぽいなぁ」とか言うかねぇ。
昔聞いた話といい、この説といいなんとか家康公を絡ませたい意図を感じる。
まぁ諸説ありますってことでしょうね。

おまちのあちこちにあるオブジェ
今回の静岡街ぶらで出会った風景がこちら↓








