灰色の空に舞う『リトルダンサー』atおうちシネマ
2000年にイギリスで制作された『リトルダンサー』。
バレエに魅了された少年・ビリー・エリオットと、家族や周りの人々との絆を描いた青春ドラマだ。
この映画を今でも時々観たくなる。
なぜなのか。
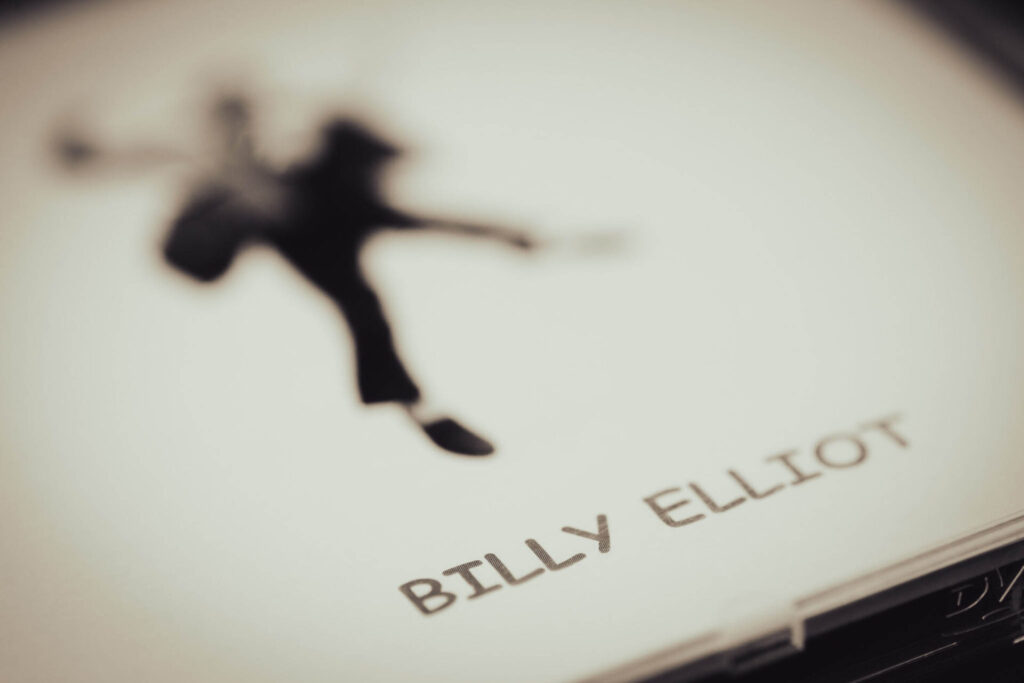
目次
あらすじ
1984年、イギリス北部の炭鉱の町ダラム。炭鉱労働者のストライキが行われ、そこに暮らす多くの人々が不安になっていた。
主人公ビリー・エリオットは、父と兄、そして認知症気味の祖母との三人暮らしの少年だ。
数年前に母が亡くなり、家族は皆喪失感を抱えていた。
ビリーは、父の勧めで町のボクシング教室に通っていたが、そこでたまたまバレエに出会ってしまう。
バレエ教師ウィルキンソン先生に促されるがまま、ボクシングブーツからトゥシューズに履き替えバレエのレッスンに参加するビリー。
ボクシングでは感じることができなかった高揚感をバレエで感じ、父には内緒でバレエ教室に通うようになる。
バレエに魅せられ没入していくビリー。
そしてまた、ウィルキンソン先生もビリーの中にあるバレエの才覚を見抜き、ビリーに肩入れしていく。
だがある時、バレエ教室に行っていたことが父の知るところとなり、ビリーはバレエ教室に行くのを禁じられてしまう。
ビリーからその報告を受けたウィルキンソン先生は、「ロイヤルバレエ学校を受験してみてはどうか」と提案する。
そして秘密のレッスンが始まる。
心で泣いている大人たちを傷つけるのも癒すのもビリー
この映画の登場人物は大人も子供もみな苦しみを持っている。
でも主人公ビリーをはじめ子供たちは、暗い世相や各家庭の困りごとを感じながらも同時に楽しみも見出し、たくましく元気に生きていた。
ところが大人たちは、ギリギリの状態で必死に生きている人ばかりだ。
ビリーの父は、信念の為ストをしているが家族を養わなければいけないジレンマがある。
一緒にストをしている長男は組合のリーダーで、過激な行動を取って身を破滅させないか心配だ。
次男のビリーを自分のような屈強な男にしたいのに、ボクシングは下手だし、母の形見のピアノを暗い顔で弾いていて、
自分の思い描いた子になっていない。
妻に先立たれたことに自分も打ちひしがれているのに、ストや家族のことで精いっぱいな毎日を送らなければいけないのは、つらく苦しいものだろう。
父だけでなく兄もウィルキンソン先生も、苦しみの中でも足を止めず一日一日をこなしていかなければならない。
そしてビリーは悪気なく、大人たちの痛いところを突く発言をする。
元々口数の少ないビリーが、大人たちが抱えている苦しみの核心に触れることを言うので、大人たちは堪ったものではない。
ビリーもつらいから気持ちはわかるが、心の中でしか泣けない大人たちにそれを言うのはやめてあげてと思ってしまう。
父もウィルキンソン先生もビリーの言葉が引き金になって涙を流すシーンがあるが、
現実社会でうまくいかないことが多い大人の視聴者は、グッとくると思う。
でも、心がボロボロになっている大人たちを癒し、希望を見出す源になるのもやはりビリーなのだ。
ビリーのバレエが大人たちを惹きつけ、ビリーの存在が希望そのものになるのだ。
ビリーの言葉で、それまでは我慢していた涙を流し、溜まっていた辛い気持ちを吐き出すことができたのだ。
パワフルなダンスシーンと音楽が暗い背景を吹っ飛ばす
タイトルが『リトルダンサー』なだけあって、本編中ダンスシーンが多く散りばめられている。
バレエダンサーを目指す少年の話なのだが、映画ではバレエより当時流行りのロックナンバーが数多く挿入歌として使われている。
UKロックに全く明るくない私でも聞いたことのある曲があちこちで流れ、映画のシーンを盛り上げる。
ビリーが踊るシーンでもUKロックがよく使用されている。
ビリーのダンスはいろいろな場面で登場するが、どのダンスにも力強さがあり、その時のビリーの心情を発露している。
普段口数が少ないビリーが、ダンスではこんなにも素直に気持ちを表現することが出来るんだと、一視聴者である自分にも伝わる大事なシーンだ。
先述したが映画の背景は、ストで揉めている最中の炭鉱の町ダラムだ。
人々はみな鬱屈した毎日を送っている。
気候的にもこの地域は、夏は涼しく過ごしやすいが、寒い冬の期間が長く風も強く曇りがちだという。
そんな暗い背景なのにこの映画を見たあとに残る爽やかさはなぜかと考える。
その答えの一つとして、挿入歌になっているUKロックの名曲の数々と、伸び伸びと踊るビリーの姿があるのかもしれない。
映画の挿入歌をまとめたwebサイトが専門的でとても分かりやすかったのでリンクさせてもらう。
爽やかさの中に漂うペーソス、暗さの合間にあるユーモア
この作品には常に哀愁が漂っている。
決して悲劇的な場面でなくても、だ。
そして、何気ないシーンにさりげなくユーモアが盛り込まれている。
このバランスが絶妙で惹きつけられるのではないか。
この「哀愁」を「ペーソス」と言い換えることが適当かを調べてみたところに、このような記述があった。
「ペーソス」とセットになって使われる言葉が「ユーモア」です。「ユーモア」とは、人を和ませるようなおかしさです。上品で知的な笑いのことです。
「ユーモア」と「ペーソス」を持ち合わせる作品は、人間味のあふれた奥深いものとなります。「ユーモア」が人を和ませ、「ペーソス」が人を惹き付けると言われています。
二つを兼ね備えた芸術作品は、時代を問わず愛される作品となります。
『「ペーソス」の意味とは?使い方から英語や類語まで例文付きで解説』
暗さの中にある輝き
爽やかさの中に紛れ込む哀愁
喜びと悲しみ
相反するものを愛おしいものとして優しく描かれているこの映画だから、折に触れて観たくなるのかもしれない。
オマケとして ~ウィルキンソン先生役の俳優さん~
主人公ビリー・エリオットを演じたのは2000人の中からオーディションで選ばれたジェイミー・ベルだ。
この作品で一躍有名になった彼はその後も多くの映画に出演し、活躍を続けている。
もう一人、気になったのが、ウィルキンソン先生役のジュリー・ウォルターズだ。
この映画と同時期に公開された『ハリーポッター』シリーズで、ウィーズリー家のお母さんを演じた俳優さんでもある。
ロンのお母さんは、家族思いの明るく元気な主婦、ウィルキンソン先生は家庭に不満を持ち、イライラを隠すこともしない女性で、それぞれの人間像は真逆にみえる。
『リトルダンサー』のウィルキンソン先生を見ながら、ロンのお母さんの姿がチラつくことは全くない。
制作時期が被っていたかはわからず、『ハリーポッター』のほうは出番が多くないため、長年俳優をしている彼女なら、
同時期に別の人間を演じ分けることなど、難しくはないのかもしれない。
が、素人からするとすごいことに変わりはない。
彼女に限らず多くの俳優が作品ごとに違う人物になりきっているので、私たち一般視聴者は映画の世界にどっぷりと浸かれるのだろう。
ジュリー・ウォルターズは、英国アカデミー賞やゴールデングローブ賞を受賞し、英国王室から勲章も授与された名女優で、コメディエンヌとしても評価されている、とてもすごい人なのだ。

